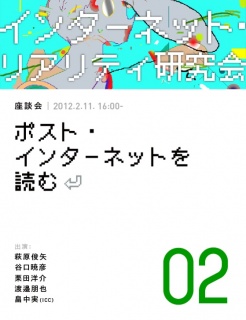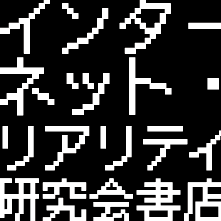
インターネット・リアリティ研究会
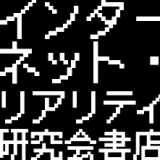
インターネット・リアリティ研究会
冊数 4 冊
紙本 0 冊
更新 2013.08.29
ジャンル アート4
インターネット・リアリティ研究会とは
インターネット・リアリティ研究会は、エキソニモ(千房けん輔、赤岩やえ)、思い出横丁情報科学芸術アカデミー(谷口暁彦+渡邉朋也)、栗田洋介を中心に、2011年7月に開催された座談会「インターネット・リアリティとは?」をきっかけに発足しました。
2012年にICCにて展覧会「[インターネット アート これから]——ポスト・インターネットのリアリティ」を企画、展覧会会期中もさまざまなゲストを交えた座談会によって議論を深めていきました。これから順次、座談会の採録やさまざまなテキスト、また映像の記録などをBCCKS等を通じ公開していきます。
-
『座談会「お絵描き掲示板のインターネット・リアリティ」』
インターネット・リアリティ研究会+ICC発行
アート
2013.08.29
『座談会「お絵描き掲示板のインターネット・リアリティ」』
インターネット・リアリティ研究会+ICC発行
アート
-
2012年1月よりICCで行われた「インターネット アート これから」展で行われた座談会シリーズの記録です。
------------------------------------
座談会「お絵描き掲示板のインターネット・リアリティ」
日時:2012年2月26日(日)午後4時
出演:谷口暁彦、gnck、虎硬、山本悠、畠中実(ICC)データ本:無料
-
『アーティスト・トーク エキソニモ + 座談会』
インターネット・リアリティ研究会+ICC発行
アート
2013.02.16

2012年1月よりICCで行われた「インターネット アート これから」展で行われた座談会シリーズの記録です。 ------------------------------------ アーティスト・トーク エキソニモ + 座談会 《ナチュラル・プロセス》と《祈》を出品しているエキソニモによるアーティスト・トークを行ないます.出品作品をはじめ,これまでの作品を振り返りつつ,《ナチュラル・プロセス》の一部として展示中の最新作《A Web Page - 403 Forbidden》をめぐる経緯について語ります.アーティスト・トーク終了後は,インターネット・リアリティ研究会メンバーも交えた座談会に移行します. 出演:エキソニモ(千房けん輔,赤岩やえ),栗田洋介,谷口暁彦,渡邉朋也,萩原俊矢,水野勝仁(ネット中継による参加) 日時:2012年2月17日(金)午後7時
- データ本
- 無料
- 読む
- 紙の本
- /
- 購入
『アーティスト・トーク エキソニモ + 座談会』
インターネット・リアリティ研究会+ICC発行
アート
-
2012年1月よりICCで行われた「インターネット アート これから」展で行われた座談会シリーズの記録です。
------------------------------------
アーティスト・トーク エキソニモ + 座談会
《ナチュラル・プロセス》と《祈》を出品しているエキソニモによるアーティスト・トークを行ないます.出品作品をはじめ,これまでの作品を振り返りつつ,《ナチュラル・プロセス》の一部として展示中の最新作《A Web Page - 403 Forbidden》をめぐる経緯について語ります.アーティスト・トーク終了後は,インターネット・リアリティ研究会メンバーも交えた座談会に移行します.
出演:エキソニモ(千房けん輔,赤岩やえ),栗田洋介,谷口暁彦,渡邉朋也,萩原俊矢,水野勝仁(ネット中継による参加)
日時:2012年2月17日(金)午後7時データ本:無料
-
『座談会「ポスト・インターネットを読む」』
インターネット・リアリティ研究会+ICC発行
アート
2013.02.16
『座談会「ポスト・インターネットを読む」』
インターネット・リアリティ研究会+ICC発行
アート
-
2012年1月よりICCで行われた「インターネット アート これから」展で行われた座談会シリーズの記録です。
------------------------------------
座談会「ポスト・インターネットを読む」
日時:2012年2月11日(土)午後4時
出演:萩原俊矢、谷口暁彦、栗田洋介、渡邉朋也(ネット中継による参加)、畠中実(ICC)データ本:無料
-
『座談会「インターネット・リアリティとは?」』
インターネット・リアリティ研究会+ICC発行
アート
2013.02.16

1991年8月6日,世界最初のウェブサイト(http://info.cern.ch/)が設立されました.それからちょうど20年が経とうとする現在,インターネットはわたしたちにとって,ごくあたりまえの存在となっています.誰かとコミュニケーションをとったり,調べものをしたり,自分の創作物を発表したり,さらにそれを批評しあったり……そこには,ネットならではの作法やリアリティが存在しているように感じられます.日々わたしたちがネットに接しているなかで,ネット特有の〈リアリティ〉を認識するようになっている,とすれば,それはどういうことなのでしょうか? この座談会では,出演者それぞれがネットに感じる「インターネット・リアリティ」ともいうべき〈リアリティ〉とは何か,なぜそう感じるのか,を探ります. -------------------------------------------------------------- 日時:2011年7月24日(日)午後6時より 出演:エキソニモ 思い出横丁情報科学芸術アカデミー(谷口暁彦+渡邉朋也) 栗田洋介(CBCNET) youpy 畠中実(ICC)
- データ本
- 無料
- 読む
- 紙の本
- /
- 購入
『座談会「インターネット・リアリティとは?」』
インターネット・リアリティ研究会+ICC発行
アート
-
1991年8月6日,世界最初のウェブサイト(http://info.cern.ch/)が設立されました.それからちょうど20年が経とうとする現在,インターネットはわたしたちにとって,ごくあたりまえの存在となっています.誰かとコミュニケーションをとったり,調べものをしたり,自分の創作物を発表したり,さらにそれを批評しあったり……そこには,ネットならではの作法やリアリティが存在しているように感じられます.日々わたしたちがネットに接しているなかで,ネット特有の〈リアリティ〉を認識するようになっている,とすれば,それはどういうことなのでしょうか? この座談会では,出演者それぞれがネットに感じる「インターネット・リアリティ」ともいうべき〈リアリティ〉とは何か,なぜそう感じるのか,を探ります.
--------------------------------------------------------------
日時:2011年7月24日(日)午後6時より
出演:エキソニモ
思い出横丁情報科学芸術アカデミー(谷口暁彦+渡邉朋也)
栗田洋介(CBCNET)
youpy
畠中実(ICC)データ本:無料
book List
-
座談会「お絵描き掲示板のインターネット・リアリティ」 インターネット・リアリティ研究会

インターネット・リアリティ研究会+ICC
-
アーティスト・トーク エキソニモ + 座談会 インターネット・リアリティ研究会

インターネット・リアリティ研究会+ICC
-
座談会「ポスト・インターネットを読む」 インターネット・リアリティ研究会

インターネット・リアリティ研究会+ICC
-
座談会「インターネット・リアリティとは?」 インターネット・リアリティ研究会

インターネット・リアリティ研究会+ICC
インターネット・リアリティ研究会
エキソニモ
思い出横丁情報科学芸術アカデミー
(谷口暁彦+渡邉朋也)
栗田洋介
萩原俊矢
水野勝仁
youpy
運営
インターネット・リアリティ研究会
http://www.ntticc.or.jp/Archive/2012/Internet_Art_Future/index_j.html
book store
その他の書店
-

-
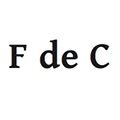
-

-
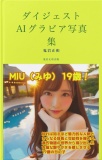
MIU、19歳の女子大生。華奢な体つきながら、しなやかな曲線美を兼ね備えた魅力的なスタイルが自慢です。 幼い頃からスポーツが大好きで、中学時代はアーチェリー部に所属。矢を引く時の凛とした佇まいは、まるで古代の狩人のよう。的を射抜く集中力と、手足の器用な動きから、運動神経の良さが窺えます。卒業後も、アーチェリーは趣味として続けています。 アーチェリーと水泳の二つの顔を持つMIUさん。凛とした一面と可憐な一面を併せ持つ、しとやかで上品な雰囲気が魅力です。まるで源氏物語の世界からいらっしゃったかのような、古風な艶やかさを感じさせる存在です。
- データ本
- 220円
- 購入
- 紙の本
- /
- 購入
-
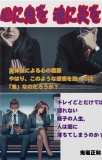
自分の父親が亡くなったというのに、悲しみすら見せない姿。 自分の父親が亡くなったというのに、葬儀の手配から親戚などへの連絡なども、誰にも頼らずにこなしてしまう冷静な姿。 自分の父親が亡くなったというのに、警察の事情聴取も冷静に対応する姿。 息子たちはどのように私を見ているのだろうか? その姿は、人間らしいのだろうか? その姿は、鬼のようには見ていないだろうか? それにしても、ちっとも悲しい気持ちにならない。 かといってスッキリとした気持にもなれない。 もちろん、楽しい気持ちなど芽生えすらしない。 虚無感。脱力感。 抜け殻のような、なのにこれからしなければならないことで、頭の中がいっぱいになっている。 ようやく、これで解放されるのだ。 本物の鬼にならずに済んだようだ。 いや、もともと心に鬼を抱いているのかもしれない。 心の鬼が表面に出てこないだけなのではなかろうか。 突然の父親の死 かかりつけ医のいない老人の死 警察による事情聴取・現場検証 死亡診断書ではなく死体検案書
- データ本
- 297円
- 購入
- 紙の本
- /
- 購入
-
-

-

-